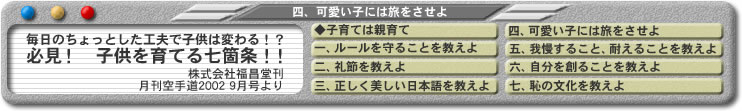 |
これは、昔から言われて来たことであり、解り易く言えば時に親から離れて、他人の中で過ごす。そして、親を少し遠くから見る機会を作り、客観的に見ることで、別の顔を発見することができる。そして、それが子供の人間的成長の助けになるということであろう。 この場合”旅”という形には、子供の年齢によって、様々な方法が考えられる。 この所、テレビ番組でよくやっている「初めてのおつかい」のように、幼児に対して十分な安全策を施した上で用件を与えて、本人に責任感や達成感を体得させるようなやり方。 小・中学生位なら、夏休みのような時、東京から北海道のように、遠い土地の親戚知人の所へ一人で行かせるとか、親が囲いこんでいないで、出来るだけその子が親を離れて何かをする機会を意識的に作ってやることは、今日のような少子化傾向の中では、逆に子離れできない親のためにも、必要なことではないだろうか。 「過ぎたるは及ばざるが如し」というのは、子育てにも当てはまることで、ぴったり寄り添って、一瞬も目を離してはいけない時期は当然あるが、子供の成長に従って少しずつ距離を取り、子供の自由な行動範囲を広げてやること、そして、それをそれとなく見守ってやれる余裕が欲しいものである。 私の出発点は、15歳の時の家出である。戦後間もない1947年、故郷広島から、一人の知人も頼る当てもない東京へ一文無しで飛び出したのである。数日、空腹をかかえて歩き廻り職を求めたが、戦後の混乱期、それは望むべくもなく、ついに力尽きて東京駅の待合室のベンチに倒れている所を、巡回に来た若いおまわりさんに救われ、連れて行かれた警察の独身寮で、炊きたての丼飯に生タマゴをかけて出され、泣きながら食べたという経験があり、今尚残る後悔は、この時のおまわりさんの名前を書いたメモを失くしたことである。 しかし、この経験がその後の私を支えてくれたことは言うまでもない。 私のケースは、特殊な時代の特別なケースかも知れないが、私の家出は私を取り囲んだ大きな閉塞状況を突き破り、脱出したいという、追いつめられた感情の爆発であったと思う。 子供が家出をする理由は、その時代により、年齢により、又、家庭環境により、正に千差万別であろう。しかし、その子供が家出をするという行動を起こす勇気は、認めてやらなくてはならない。 但し、昨今テレビで報じられているような、単なる馬鹿娘のプチ家出などは論外であり、それこそ親の顔が見たいものである。 家出という行為は、その子供にとって、良くも悪くも、その親の規範から脱出したい、仮にそれが単に可能性の問題であったとしても、自分一人で生きてゆきたいという、独立願望の現れであり、親はうろたえることなく、できれば大きな視野の中で見守ってやれることができれば最高である。 30歳を過ぎても結婚をせず、親に寄生している情けない連中より、余程増しと考えるべきである。結果として、その子供が自分の意志で、自分自身の生き方を見つけることの手助けができたら、最高の子育てというべきであろう。 |